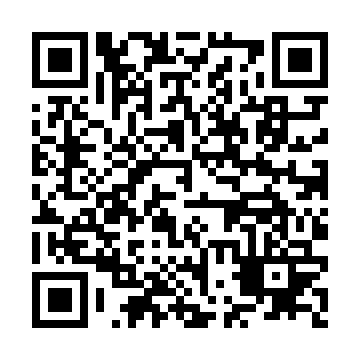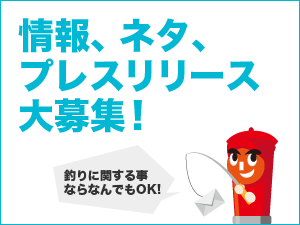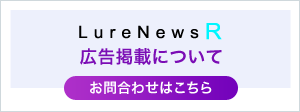山本康平( Kohei Yamamoto) プロフィール
こんにちは、山本康平です。普段はティップランなどを行うガイド船の船長をしています。もちろん、私自身もティップランの釣りが大好きで日々スキルアップするべく現場で鍛錬しています。
さて、そんな私のライフワークの1つとなっているティップランの釣り。今回は私が日頃、ティップランの釣りで大事にしているキモをご紹介させていただきます!
ティップランをこれからはじめてみたいと考えている方や、はじめたばかりの人、さらには、まだまだスキルアップを目指しているベテランの方にも、少しでもためになる情報をお伝えできればと思います。
ティップランエギングとボートエギングとの違い

まずは、ティップランの釣りとは、そもそもどういう釣りなのか? 全体像から説明させていただきます。
オフショアのエギングを経験したことがない人にとっては、ティップラン=ボートエギングと考える方がけっこうおられるようですが、実はオフショアのエギングは、大きく分けると、「ティップランエギング」と「キャスティングボートエギング(以下、ボートエギング)」という2つに分けることができます。

ボートエギングは、キャスティングしシャクって水深10m前後までを攻める釣り
では、ティップランエギングと(キャスティング)ボートエギングとの違いなんですが、違いはズバリ「狙う水深」なんです。
ボートエギングは、水深10m前後までを攻めるのに対し、ティップランエギングは15m以上の水深を狙います。
そして、ボートエギングは基本的にはキャスティングし、エギをシャクって動かして操作します。
「決まったそのボートポジションから、どう攻めるか?」「…でもオカッパリと違って足元としてのボートは常に動く」というような要件が加わるので、アングラーの経験値と技量も問われることになります。
とはいえ、アングラー自身が演出する「シャクリ&フォール」で誘うのが基本なので、ボートエギングはオカッパリエギングの延長線上にあると言えます。

ティップランエギングは30~50gの専用エギを使い水深15m以上の水深を船と潮の動きに連動した攻め
それに対しティップランエギングは、15m以上の水深を狙うので基本的にキャストをしません。
そしてエギをボトムに到達させるために30g~50gのエギを使います。場合によってはヘッドにウエイトを装着し、さらに重いものを使用するので頭から突っ込むような姿勢で沈みます。


船はアンカーをかけることなく流されるので、エギの動きは船の動きやスピードに連動して大きく影響されます。
すなわち、アングラーの意思伝達によるシャクリやフォールよりも船と潮に動かされてしまうと言っても過言ではありません。
逆に言えば、条件とポイント次第では、誰でも比較的イージーにレッドモンスターと呼ばれるような3キロ、4キロのアオリイカに遭遇するチャンスがあるんです。



ただ、ティップランエギングでも海中にエギがあれば、大型のアオリイカが勝手にエギをバンバン抱きに来てくれるわけではありません。やはり結果を出すためにはキモがあります。重要なキモが2つあるので、そのキモを1つ1つ紹介していきます。
ティップランのキモ その1
「ボトムを確実にとること」
まず1つ目のキモなのが「ボトムを確実にとること」。
これはティップランエギングを楽しみ、結果を出す上での必要最低条件と言えます。
15m以深のディープのボトムをとるために、ティップランではオカッパリやボートエギングとくらべると、かなりウエイトのある専用エギを使います。多用するティップラン専用エギの重さは30g~50g前後。
もしこれでボトムがとれない場合は、ウエイトヘッドを装着します。無理してボトムがとれない軽いエギを使うくらいなら、何しろ「ボトムを意識すること」! ティップランではこれが超重要なことなんです。

ティップランのキモ その2
「アタリを逃さない」
もう1つのキモなのが「ティップラン独特のアタリを逃さない」こと。
ティップランエギングではエギも重く、船が潮に流されて常に動きます。なのでアオリイカがエギにコンタクトしてくれる時間がとても短く、加えて大型のアオリイカは警戒心が強いのは言うまでもありません。アタリの出方がオカッパリやボートエギングとは明らかに違います。そんなティップラン独特のアタリを逃さないのがキモになってきます。


ティップランででイイ釣りをするには、どうすれば良いのか?
ではティップランでイイ釣りをするには、どうすればイイのか?
どんな釣りでも同じだと思うのですが、オモリは軽ければ軽いほうが魚(イカ)に食わせる(抱かせる)のは有利になります。
ティップランでも同様で、ボトムを感知できるギリギリのレベルで、少しでも軽いエギを使うことがヒット率を上げることにつながります。
そうすることで、根掛かり回避やアクセントでシャクリを入れた後のフォールスピードもスローになりますし、アオリイカがコンタクトした時に、イカが感じる違和感も軽減されます。

ただ、ティップランエギングの場合は「ボトムがとれる」ことが大前提になるので、単に軽くすればよいというわけではありません。そのためには、エギの動きを把握し、どれだけコントロールできるかです。ここはアングラーの技量が左右するところですので経験が必要になるでしょう。

ティップランではロッドの役割が非常に大きいと考えています!
さて、そんなボトムを感知したり、エギの動きを繊細に感じとるためには私的にはロッドの役割がスゴく大きいと考えています。
では、どんなロッドがイイのか?なんですが…。
まず一般的なティップランエギングのロッドというのは多くがソリッドティップが採用されたモノになっています。
それはロッドを握る手にアタリを伝える「手感度」ではなく、ソリッドテッィプに出るアタリを目でとらえる「視覚感度 (目感度)」を意識しているからです。
しかし、私の経験では「視覚感度」ばかりを重視しすぎるとティップ部分の動きでアタリの信号を吸収してしまい、手元に伝達する「手感度」は確実に悪くなると実感しています。
ティップランで愛用しているのは開発に参加したチューブラーティップ採用!ブラックライオンの『75M』と『75MH』
そんな中で、私がティップランで愛用しているロッドなのが私自身、開発に参加させてもらったティップラン用のチューブラーティップのロッドなんです。

チューブラーは断面の真ん中が中空になっている特性上、ソリッドティップのように極限まで細くすることはできません。
ただ、金属の棒とパイプ状のものを叩いた時の響き方が違うのと同じように、同じ素材ならば信号の伝達能力はチューブラーの方が優れているんです。
そんなチューブラーティップを使ったティップランロッドを作りたいと思い、試行錯誤を続けた結果、チューブラーティップに採用する素材を厳選することで、ソリッドティップのような「視覚感度」と手元への「伝達感度」を両立させることができたんです。
そうやって生まれたのがブラックライオンのティップランロッド『75M』と『75MH』なんです。
わたくし、山本康平は今現在、その『75M』と『75MH』の2本を使っているのですが、その日の状況や狙う水深で使い分けています。

またこの2本のコンセプトである「次世代エギング」を見据えて、ティップの変化を「視覚感度」でとらえるだけでなく、手元に伝わる「手感度」を進化させた「抵抗感度」で、微細なアタリが捉えられるようにしてあります。

「抵抗感度」とは、どんなものなのか?
ちなみに「抵抗感度」とは、どんなものなのか? を少し詳しく説明すると…。
ティップランエギングでは船は常に動いています。
また海中では、エギが潮を受けて抵抗があります。
その船の動きと潮の抵抗の強弱を明確に感じることで、かすかな抵抗変化も逃さないのです。
ライトゲームなどでよく言われる「違和感」や「ヌケ」のアタリに対して、自信をもって感じられることが結果を大きく違ったものにします。
「抵抗感度」…これは、ブラックライオンのオカッパリエギングロッド『ラーテル77』でも強く意識しました。
潮を感じて海中の様子を把握するのはもちろんのこと、アオリイカがエギを狙い定める気配までも感じる…これこそがブラックライオンの追究するロッドなんです。