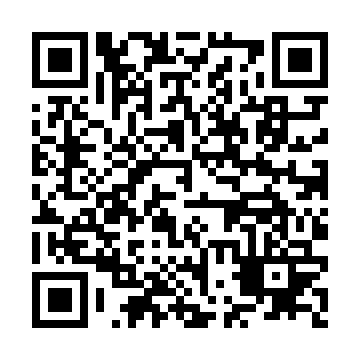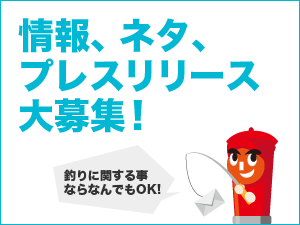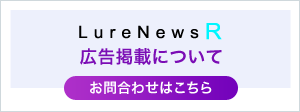今江克隆のルアーニュースクラブR「ライブサイトのニュースタイルとオールドスタイルの限界」 第1236回
今週は、今年のTOP50開幕戦で痛切に感じた明確な時代の変化について書いてみたい。
7年ほど前に登場したライブスコープは、今までのバスフィッシングの常識、シーズナルパターンやバスの生態の常識、さらにはシャロー、ディープという概念すら根底から変えてしまうほどのゲームチェンジャーとなった。
今まで春のシーズナルパターンでは非常識だったドン深の垂直岩盤の中層でプリのビッグバスを狙って釣れる事実、さらには「シャロー」の意味は岸際だけではなく、何もない湖のド真ん中表層2mも水面を逆壁としたシャローであり、何もなくてもエサがいればバスは年中、実はどこにでもいるという、バスの生態の常識も完全に覆った。

桜が満開の春に沖のディープで釣りを展開するなど、10年前に誰が考えただろうか。ライブソナーの登場はバスフィッシングの常識を変え、パターンフィッシングやシーズナルパターンの概念さえ完全に崩壊した。もはや過去の経験は邪魔にしかならない
もはや浚渫やボトム変化のあるオフショアでなくても、皿状の湖では喰えるベイトさえいれば、バスは水深や地形にすら無関係にどこにでも存在することも分かってきた。
例を挙げれば、かつてバストーナメント黎明期に入鹿池や津風呂湖に幾度も通った自分の経験からすれば、30年前に激ムズでバスも激ヤセ、5尾1,800gも釣れば余裕で優勝だった湖が、今や3尾6kgも当たり前、しかも皿池状の何もないボトムのど真ん中、中層でバンバンとブリブリのデカバスが釣れる現実は、昔のバスの生態と常識から考えればあり得ない出来事にすら思えてしまうのだ。
果たしてそれが大昔からいたが誰も気が付かなかったのか、人為的プレッシャーからの劇的な行動変容で居場所が変わったのかはわからない。
だが、今までカバーや地形変化から常識的にバスが高確率でいると信じられていた場所より、はるかに「そこはいないと思っていた場所に実はいた」のである。
それを暴いたのがバスフィッシング新時代のゲームチェンジャー「ライブスコープ」、「ライブソナー」であることは間違いない。
ライブサイト新次元に突入
そして昨年、そのライブソナー技術は明らかに新たな次元に突入したと自分は感じている。
自分がライブソナーを本格導入したのは約6年前の2019年。
2020年のコロナ休止を挟み、2023年にはTOP50桧原湖戦でライブサイトによって表彰台を獲得。
当時、国内最高峰ライバーの青木唯プロの横に立てたことはライブソナーでも若手と互角に戦える大きな自信となった。
だが、それは桧原湖でエレキのスポットロック機能とローテーターを使ったライブサイトであり、今でいえば最も「楽なライブサイト」でしかなかった。
この年から海外でいきなり結果を出した藤田京弥プロ、国内で驚異的強さを見せた青木唯プロの影響で、若者たちのライブサイト技術が劇的にNEXT LEVELに進化していったことに、ローテーターライブで少し満足してしまった自分は気づくのが遅れてしまった。

桧原湖で青木唯プロの横に並べた時、自分もライブ世代に追いつけたかと思えたが、それはライブ沼の入り口に立ったに過ぎなかった

シャフトに端子1個、ローテーターに1個、16インチモニター2個で挑んだTOP50野村ダム戦。だが野尻湖や桧原湖以外でローテーターを使っているようではライブサイトは初心者レベルである
NEXT LEVELとは何なのか
奇しくも自分がライブサイトを導入した年は、イマカツ唯一であり生粋のライバーである当時16歳の藤川温大プロがライブサイトに没頭し始めた年でもあった。
その藤川プロが23歳となりTOP50に昇格、初参戦し決勝でエンジントラブルを抱えながらも優勝争いを演じたことは、デジタルネイティブならぬライブサイトネイティブのプロ達のライブ技術が想像を超えるレベルに進化していたからに他ならない。
では、そのNEXT LEVELとは何なのか、自分が現実に目の当たりにし、同時に本人たちから直接聞いた前世代ライブとの違いを簡単に解説しておこう。

TOP50プロの99%が装備するライブスコープ、ライブソナー。ライブの釣りに16歳から親しんでいる藤川プロや若手たちにしてみれば、キーパー程度ならライブで釣ることなど造作もないことだった
まず、今までバスをライブソナーで見つけてそこにルアーを正確にしつこく通すことを「オジサンライブ」と称するなら、NEXT LEVELライブの最も大きな違いは、「バスを直接見つけるのではなく、最初から最後までルアーを見る」ことだろう。
TOP50野村ダム戦での上位インタビューでも、初日朝はバスがライブに映ってイージーだったが、すぐにバスがプレッシャーで動かなくなったのか別の魚しか映らなり、ルアーでバスを引っ張り出した」と語っていた。
これは藤川プロも同じことを言っており、事実、昨年の七色ダム開幕戦で優勝した吉川プロが初めてこの「ブラインドライブサイト技術」に言及したと記憶している。
すなわち、スコープを頻繁に回しバスらしい魚影を見つけては、それを狙って正確にルアーを届け、見失っても近くにいると信じて誘いを続けて釣る「オジサンライブ」ではなく、ルアーを着水からプロダクティブゾーンまでモニターで凝視し続け、バスが向こうから出てくるまでそれを全キャスト繰り返すのが基本だ。

今やコックピットにもライブソナーを2台セットし、デッドスローで左右のバンクに直角に当てることで、地形もろともバスそのものやベイトも見つけるセッティングが主流だ。下は今も使っている自分のオールドスタイル
それはまるでビッグベイトで隠れているビッグバスを引っ張り出し、目視で確認、戻る場所を覚えておいて本番に一撃で狙う、自分が2021年弥栄戦で「レイジー9」と「メタルクロー(スピン)」の合わせ技を、見えない水深で見えないバスを釣るのに行っているに極めて似た方法だ。
この自分のアナログな方法は、バスが出てきて喰わないことも前提で、時間と一度見せたルアーから大幅にルアー変えてタイミングで狙う釣り方だ。
だがNEXT LEVELのライブサイトは、その行為が目視不可能な水深でバスが追ってきたことを認識できる。
ゆえにバスからはボートやアングラーが見えない、もしくは見えにくい場所にいるため警戒心が薄い。
これはリアルサイトフィッシングで、バス自らが見つけたエサ(ルアー)には警戒心が緩いというアプローチのキモと同じだ。

NEXT LEVELのライブサイトは、もはやバスを探して狙い撃つのではない。その概念はある面、ビッグベイトやピクピクをチェイスしてきたバスを最終的に喰わせてしまう技に通づる気がする
さらに上を行く「喰わせ術」
昨年、TOP50開幕七色ダム戦での吉川プロのライブサイト圧勝劇は、「ルアーを自ら発見して出てきたバスは喰いやすい」という、水中のバスを直接見つけるというライブサイトの逆を行く、ルアーをライブで見てバスが出てくるのを待つという逆説のテクニックだった。
このテクニックの最も難しいところは、朝から晩まで毎キャスト、ルアーを着水から想定プロダクティブゾーン通過まで、照射角度わずか20度にも満たない狭い音波幅を当て続け、終始見失わず追い続ける想像を絶する執念とエレキ操作能力(脚力)がまず最低限必要になる。

ルアーをモニターに捉え続けるために、藤川プロのボートセッティングは16インチ1台と極めて軽量シンプル。画面が増えたり重さでバウが下がると、情報が増えすぎ気が散るうえ、投影精度も落ちるからだそうだ

若手ライバー達はペダルの操作のために靴にも徹底的にこだわっている。藤川プロはこの靴一択だそうだ。ペダルの踏み方にも並のライバーとは異質なものがある気がする。少なくともファイティングチェアを使っていては話にならない
そしてさらに難しいことは、バスが出てきた時にどうやって喰わせるか、どこで喰わせるのかという問題だ。
自分が最も強く感じたライブサイトの問題は、今やNEXT LEVELライブですら「追ってきても喰わせられない」「ギリギリで見切られる」という現象が最近多発し始めたという問題だ。
そこのさらに上を行く、「喰わせ術」が今やハザマライバー(ライブとアナログの混合型)とネイティブライバー達との大きな結果差となって表れてきた。
それが今のライブサイト社会の格差なのだ。

野村ダムでは滅多にお目にかかれないプリのビッグバス。藤川プロは岩盤水深3mから出てきたこのバスを、なんと水深12mで喰わせていた
そういった意味では、野村ダム戦で優勝した梶原智寛プロがライブを切って(スイッチで電波遮断のスリープ状態にGARMINはできる)釣った事実は、このパターンをさらに超ハイレベルに極めたとんでもないテクニックといえるだろう。
これは前世代アナログ釣法で完勝したのとは、次元が全く違うと自分は思っている。

このようにバスがモロ映りの状況でのライブサイトはTOP50では通用しない。プレッシャーで動かなく(映らなく)なったバスをルアーで引き出し、誘い込み、驚きの操作技術で喰わせるのがNEXT LEVELだ
ライブの達人が使うルアーは?