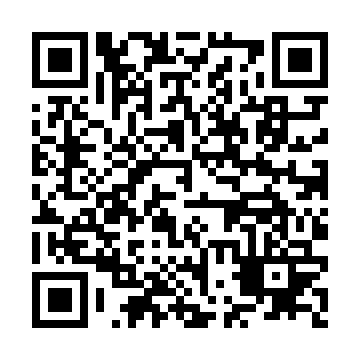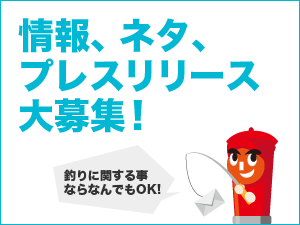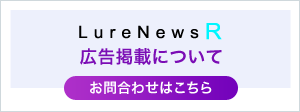今回はインクステレビのQ&A企画【レオンの深釣り堀】に寄せられたご質問をピックアップしてお届けします。

レオン 加来 匠(Kaku Takumi) プロフィール
魚の着き場所(ポイント)を考える上の基本を教えてください
レオン様、インクスレーベルの皆様いつも楽しくワクワクする商品、情報発信ありがとうございます。質問をさせていただきたく思います。メイン魚種、釣方はおかっぱりではメバリング、アジング、エギング。ボートではティップランエギングと一つテンヤマダイ、ミドルゲームです。エリアは呉市とびしま周辺です。
日々勉強させていただくなかでレオンさんが口酸っぱくおっしゃってる固定観念にとらわれないを意識するようにしています。結果、私の中で大きく変わったところはポイント選び、ルアーの大きさとカラーです。
ポイント選びはメジャーポイントじゃなく、誰もやってないとこでも釣れるポイントがあちこちあることがわかったことと、探して考えて釣果がついてきた時の喜びです。ルアーはワームを含めボリュームに対する抵抗がなくなり大きいものを好んで使えるようになりました。例えばSPM55より75やワームも同種類なら2インチより3インチをメインに使用したりです。カラーはクリア系がメインでしたが黒やチャート系の俗に言う、売れないカラーもバンバン使用でき釣果も変わらないか、もしかして上がってるかもという感じです。全てではありませんが、今までと違うことをすると違う答えが返ってくることが分かりました。
そんな中、ティップランエギング時、私の中である発見があり、今回の質問をさせていただきました。水深15mほどでフラットな海底部に1mほどの盛り上がりがありまたフラットになる場所で、上げは西から東、下げは東から西の潮流。どちらの潮でもかけ下がりで圧倒的にヒットします。私なりの考えではイカが潮下の影に潜んで弱って流されてくるエサを待っているのではないかと思うのと、同時に発見ではなくあたり前の事で私に知識がなかったからなのではとも思いました。
そんなことから基本的な知識で知らなかったこともまだまだあるのではと感じています。俗に言う普遍的な考えになるかもしれませんがレオンさんの考えで魚種によるポイントの立体的な考え方、風、気温、気圧、水温、時期〔春、夏、秋、冬など〕天気、川の流れ込み状況などと魚の行動との関係性である程度の原則みたいなものを教えていただきたく思います。基本的な考え方を理解し、その上でより枠を超えた考えもできるのではないかと思い質問させていただきました。下手な文章、長文になり申し訳ございません。なにとぞよろしくお願いいたします。
…いやいや、すごく考えながら釣りをされているのが伝わってきますね。
とくに 「固定観念にとらわれない」 という意識を持って試行錯誤されているのは素晴らしいです。それでは質問にお答えしていきましょう。

①:ティップランでの発見について
潮がかかる地形の変化にイカが着くのは間違いないですし、「かけ下がりで圧倒的にヒットする」というのは、 潮の流れと地形の関係をしっかり理解できている証拠 ですね。この方が考えている通り、 イカが潮の影になる場所に潜んで流れてくるエサを待っている可能性は非常に高いです。
また、 「どの潮でもかけ下がりでヒットする」ということは…
・潮上ではなく潮下側にポジションを取るイカが多い
・ 潮流が変わっても「待ちの姿勢」を崩さないイカがいる
というパターンがデフォルトであるとも言えます。そしてティップランの場合、エギの落とし方やドリフトのさせ方を調整すると、より自然なアプローチとなります。
②:魚種ごとのポイントの立体的な考え方

魚種によってどのような場所に定位しやすいかを 「地形」「潮」「ベイトの動き」「環境変化」 で考えてみましょう。
地形:岩礁帯、堤防際、ゴロタ、かけ上がり、ストラクチャー周辺。メバルは「壁」や「ブレイクライン」に着くことが多い。また、アジは回遊性があるが、流れのヨレや岸際の変化に集まりやすい
潮:メバルは 緩やかな流れがある場所 に溜まりやすい(激流すぎると嫌う)。一方アジは 潮目や流れの変化を好む(流れが強いとベイトがたまりやすい)
ベイト:プランクトンが溜まりやすい場所にアジが集まりやすい。メバルは小魚や甲殻類を狙いやすい位置に定位する。
環境:冬は深場に落ちる個体が多いが、シャローに残る個体もいる。気圧が下がると浮きやすい傾向(特にメバル)。
立体的な考え方…メバルやアジは 「潮の影」になる場所や流れのヨレに定位しやすい」 ので、ルアーの通し方として ヨレをなめるようにドリフトさせる と効果的。
地形:砂地+岩礁帯の境目、かけ上がりやフラットな場所の変化(小さな駆け上がり・駆け下がり)。水深10m以上の沈み根周辺。
潮:潮上から潮下に流れてくるベイトを待ちやすい。かけ下がりの「影」になる場所で待機しやすい(ティップランの発見と一致)。
ベイト:小魚(アジ・イワシ)やエビ類が豊富な場所が狙い目
環境:気温が下がると深場に落ちやすいが、朝夕はシャローにも出る
立体的な考え方…イカは 「待ちの姿勢」 になることが多いので、エギのフォールを意識的に長く取る or 一度浮かせて再フォールさせると効果的。
地形:かけ上がり・かけ下がり・フラットな砂地+根が点在するエリア。ブレイクライン沿いの潮がぶつかるポイント。
潮:潮がしっかり流れるエリアが基本(反転流・ヨレを狙う)。「潮の影」になる場所で待ち伏せしていることが多い。
ベイト:エビ・カニ・小魚を捕食するため、海底の変化を活かす。
環境:水温が高いと活性が上がり、低いと動きが鈍る。気圧が急変すると食いが落ちることがある。
立体的な考え方…潮の流れがある場所で、「かけ上がり→フラット→かけ下がり」 の流れの変化を活かし、ベイトがどこでたまりやすいかを意識する。
③:環境要素と魚の行動の関係

風:強風時はベイトが岸際に寄りやすく、メバルやアジのシャロー依存度が増す
気温:急変すると魚の活性が落ちるが、徐々に変化する場合は適応する
気圧:低気圧時は魚が浮きやすい(特にメバル)
水温:冷たい時期は深場、暖かい時期はシャローに移動しやすい
時期:春は産卵後の回復個体が多く、秋はベイトパターンが変化しやすい
天気:曇り・雨の日は表層の魚の警戒心が薄れやすい
川の流れ込み:プランクトンが集まりやすく、ベイト→ターゲットの順に寄ってくる
まとめ
「違うことをすれば、違う答えが返ってくる」 というのは本当に重要な考え方です。
釣りでは 「地形+潮+ベイト+環境」 を総合的に考えると、より狙うべきポイントや攻め方が見えてきます。今回のティップランの発見のように、 「こういう場所で釣れる理由」 を一つずつ理解すると、どの釣りにも応用できるようになります。
これからも試行錯誤しながら、さらに釣果を伸ばしていってください!