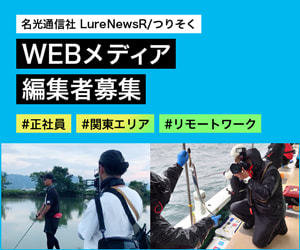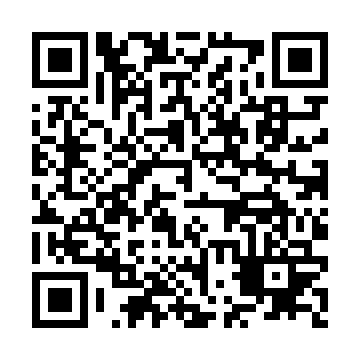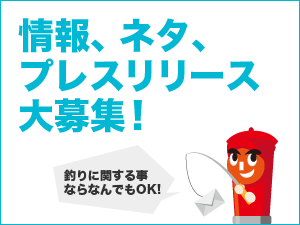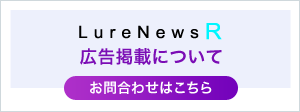レオン加来匠 原点を辿る ~幼少期に出会った2人の真の師~
2026年、「釣りと人生」という書籍が発刊されます。
出版社の手による物ではなく、一人の釣り好き青年(26歳)が動画カメラを片手に全国の釣り人を訪ね歩き、インタビューして一冊の本にまとめるという自費出版モノ。なんと僕にも出演オファーが来たのですが、企画内容をお聞きして驚くと同時に深く感動して参加させていただきました。
本誌には普段なかなか知り得るきっかけが無い和竿作りの達人や、フライビルダー・ルアービルダー・バスプロなど錚々たるメンバーが登場する予定のようですので、僕もとても楽しみにしています。
ということで、今回は僕の釣りの原点であり出自ともなっている釣り人とのエピソードを少しだけ綴ってみました。

レオン 加来 匠(Kaku Takumi) プロフィール
レオン加来匠の原点
釣りという、本能の部分まで帰結する欲であり生きる術であり、あるいは世界に冠たる日本の文化でもあるこの遊びを、私の血肉にまで染み込ませてくれた者たちがいる。
あくまで私の幼少期(5歳〜10歳位程度まで)の事ではあるが、それは「隣の爺ちゃん」から始まり、「新田のガンゾウ」と呼ばれたガキ大将を経て、「青沼の妖怪」と称された稀代のヘラブナ師へと続き、さらには釣りではなくとも、手づかみで大鯉を捕獲することで全国にその名を轟かせた「鯉獲りまあしゃん」にまで及ぶ。
彼らの消息は今ではたどることも叶わない。ただひとり、「鯉獲りまあしゃん」だけは、その異名とともに歴史に刻まれ、ウェブ検索をすれば今もなお浮かび上がる。
そして、やがて私は何の運命であろうか長じて釣り業界にその名を響かせる重鎮たちにも師事することになる。しかし、私にとって真の師であったのは、幼き日に出会った名人たちであったように思われる。そして彼らのことを、今一度、思い出とともに綴ってみたくなった。
私の釣りの原点をたどれば、やはり父の存在に行きつく。
父は詩人・北原白秋の弟子であり、また熱烈な釣り人でもあった。地元の新聞(西日本新聞)に「釣り文士」としてエッセイを寄稿していたが、それは技術指南ではなく、読み物としての趣きを重んじたものだった。だが、父はある事情から文壇を離れ、大手の生保会社に身を置くようになった。そのため、私が小学校低学年のころは家にいることが少なく、記憶のなかでも遊んでもらった事はとても影が薄い。そんな父が、ある夏の日私を釣りに誘った。小学校二年の夏休みだった。しかし、家を空けがちな父は、私がどれほどの釣り人であるかを知る由もなかった。
子供が何を気取っているのかと思われるかもしれないが、これには訳がある。当時の私は疎開先農村の母屋の主である“隣の爺ちゃん「源じい」”の愛弟子だったのだ(つり人社刊:うさぎ美味しいかの山)

源じいは名うてのハンターであり釣り名人でもある。源じいは山鳥やタヌキやウサギのワナの作り方などを私に教え込んでくれた。幼少の私は実に熱心な弟子だった。五歳から九歳までの間に彼の技術を学び、さすがにタヌキは無理があったが、実際に兎も山鳥も獲れるようになっていた。そして同時に釣りに関しても漬け鈎や掛け鈎を初め、カイボリや梁掛け漁など数々の技法を仕込まれた。
そんな爺ちゃんのもとで育った私は、小学一年生にして「釣り鈎の自作」ができるようになっていた。
使い古された木綿針やミシン針を手に入れると、ペンチで挟んで蝋燭の炎で焙り、源じい自作の釣り鈎製造機である「厚板」に打ち込んである、数本の釘に絡めて“つの字”に曲げる。さらに針先を少し叩いて平打ちにし、お尻を潰してチモトを作る。再び焙って形を整え、仕上げに機械油で焼きを入れる。そして最後に砥石で針先を研げば、立派な釣り鈎の完成だ。
鈎だけではない。竿もだ。裏山から爺ちゃんが選び抜いた「雌竹」を切り出し、枝を丁寧に払い半年以上乾燥させる。程よく乾燥させたら囲炉裏で節を焙りながら専用の器具で形を整え、鯨の脂を塗り重ねる。こうして仕上げられた竿は、まさに「業物」だった。今の小学生には考えられないことだが、昔の子供はこういうことをけっこう難なくこなしたものだった。
——そんな私を、父は初めての海釣りに誘った。長崎県大村湾のハゼ釣りである。
釣り方を説明をする父を見て、子供心にも「父は私を甘く見ている」と感じた。ハゼなら川でヨシノボリやドンコをしこたま釣り慣れている。絶対驚かせてやろうと息巻いた。しかし、結果は父の半分ほどしか釣れなかった。とても悔しかった…。
だが、父は私の釣果にかなり驚いたようであり、それ以来私を釣りに連れ出すことが増えた。中学に上がるまで、あちこちの釣り場に連れて行ってもらったが、不思議なことに技術的な教えはほとんど受けた記憶がない。いや、むしろ技術面では現場で出会う地元の名人たちから学ぶことの方が多かった。たとえば、ヘラブナが潜む「青沼の石切り場跡」で出会う妖怪オジサンや、雷魚釣りの達人である中学生のガンゾウなどだ。
一方、父から教わった(五年生の夏)ことのなかで今もなお心に響いているのは哲学だった。文士ならではの禅問答のような表現だったが、何のために釣りをするのかを正座までさせられて聞かされた。
「釣りは、魚を釣るのではなく心の健康を釣るものだ」
「釣りは、生涯通じて自分を探す旅だ」
「今は分からないだろうが、この二つは覚えておきなさい」と…。この二つの言葉は、今も私の心の奥底に鳴り響いている。
ともすれば、利に侵され競に走り挙げ句の果てには争の因ともなってしまう釣りという遊び。この負の部分を父は釣り好きとして心から憂いていたのであろう。