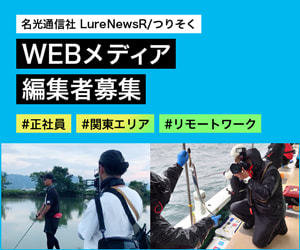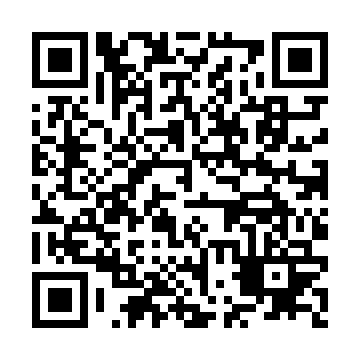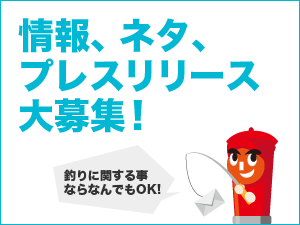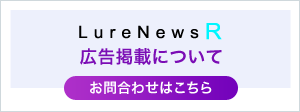皆さんこんにちは!
東京湾奥エリアで活動するメガバススタッフの加藤光一です。
今回は、早春のナイトゲームでシーバスを狙う必殺のパターンを紹介いたします。
東京湾シーバスゲームの早春の魚の動きについて
東京湾奥における早春のシーバスの多くは、冬季の産卵を終え湾奥各所に戻ってくるアフターの季節です。
1月後半から始まる河川でのバチ抜けパターンを筆頭に、アミパターンやイナッコパターン、イワシやコノシロ、サッパといった回遊ベイトのパターンといった様々な生物達を捕食するシーバスを狙うパターンが始まります。

早春の東京湾奥でチャンス大なのがボトム付近を狙うハゼパターン
そんな様々なパターンが始まる早春の東京湾奥で私がオススメしたいのが、ボトム付近を狙うハゼパターンです。
東京湾の汽水域はハゼ釣りのメッカとしても人気がありますが、ハゼはシーバスのメインベイトの1つでもあるのは皆さんご存知の通りです。
越冬したマハゼは12~17cm程度と大型で、シーバスにとっては食べ頃サイズであり、ボトムに定位しているので体力の落ちているアフターシーバスが回遊せずに探せるエサでもあります。

砂泥ボトムに通年生息しているハゼ類は、バチやアミの様に流れの有無や強い風、特定のジアイに影響されることが少なく、イワシやコノシロ、サッパの様に群れの回遊の有無に左右されないという安定して狙える大きなメリットが有ります。
なので仕事や家庭の事情で理想的な時間に釣りに行けない…またはバチ抜けパターンで混みあう釣り場がちょっと苦手というアングラーさんにもオススメなパターンです。
また、回遊する小魚を待ち受けて捕食するシーバスを狙うパターンとは異なるので、流れが効いているタイミングや橋脚の明暗部といった人気の場所ではなく、オープンエリアで十分に成立する釣りなので釣り座が確保しやすく自分のペースでシーバス釣りを楽しむことができる場合が多いのも魅力です。

ハゼパターンのルアーについて
早春のハゼパターンにオススメなルアーが、スローシンキングの細身のミノーやシンキングペンシルです。
特にX-80シリーズが圧倒的な信頼感と実績があり、厳寒期から早春のハゼパターンでは10年以上前から主力として活躍してくれているルアーです。


X-80 SWまたはX-80SW LBOを軸にボトム付近をできるだけスローに誘うのがこのパターンの基本になります。

低水温期は捕食者であるシーバスもベイトとなるハゼの動きも活発ではないので、ルアーがボトムタッチしてルアーのアクションが激しくなるのはシーバスに警戒心を与えてしまう場合が多いのでロッドポジションの高さでルアーの通過するレンジをコントロールしてください。
この時、馬の背やブレイクラインの駆け上がりを狙うので、必ずしもルアーがボトムべったりを通過する必要はありません。
ボトムギリギリを狙って根掛かりしてしまったり、ルアーがボトムに当って必要以上に動いてしまうことを避けるという意味でも、ボトムから10~50cm程度を通すイメージでアプローチを行うと良いです。
ハゼは流れてくるエサを捕食する際にボトムから数10cm浮上することが多々あります。そういった動きのハゼをイミテートするイメージです。
また、ロッドを高く上げてもボトムタッチしてしまう場合は少しレンジを上げるためX-80SW LBO Shallowといったシャローモデルがオススメです。

加藤のファーストチョイスはX-80マグナム

ちなみに私のファーストチョイスルアーはX-80マグナムです。厳寒期~早春のランカーハンティングでの釣果に長けており、2025年も2月末時点でX-80マグナムでは97cm筆頭に3本のランカーシーバスをキャッチすることができています。


ルアーのカラーについてですが、発色の強いアピール系のカラーを用いても離れた場所に居るシーバスがルアーを見つけてもあまり追って来ないイメージなので、澄潮の冬季~早春は特にこだわりはないのですがナチュラル系もしくはクリア系を使う場合が多い傾向にあります。
潮回りや潮位による釣果の出るジアイにシビアさは無いように感じていますが、干潮で干上がってしまうような場所だと、回遊性の低いアフターシーバスがシャローに戻って来るまでに少々時間が必要なので、上げ潮中盤以降に釣果が出やすい印象です。

干潮時に干上がらない水深のある場所では、潮位やタイミングよりも、使うルアーがスローにボトム付近を通せる水位もしくは釣り場の形状を重要視すると、たとえ潮止まり前後でも釣果に繋がりやすいです。

空海のタックルについて
この釣りでのオススメのロッドを1本選ぶなら、空海シリーズの『CK-96MS』です。
通年トップウォーターペンシルからイナッコパターン、バチパターンといった多彩なアプローチにも対応できるバーサタイルなロッドであり、わたくし加藤の愛竿の1本でもあります。
次に大型のシーバスに狙いを定めたいなら空海シリーズ最強のスピニングロッド『CK-83XXHS』がオススメ!

実はここ2年間、オールシーズン 『CK-83XXHS』をメインにシーバスを狙ってきたのですが、その間50本以上のランカーシーバスをこの『CK-83XXHS』でキャッチすることができています。
100gのルアーをキャストできる強いロッドですが、決して『硬い竿』ではなく適所にしなやかさを併せ持っていることはキャッチ率の高さが証明してくれていると感じています。
ロッドの特性的に100gのルアーを余裕をもってキャストできるという部分が主にフォーカスされがちですが、実は13gのホムラ86やゾンクシンペン77、X-80SWといったミドルサイズのシンペンやミノーも十分な飛距離で『普通に』シーバスを狙う事ができてしっかりと釣果に繋がっています。

さらに、メガドッグ180やアイスライド187RSWなどのビッグベイトもその日の状況によりロッドを変えずに狙えるというバーサタイルな特性を持っています。

・10g以下~40gのルアーを主に使用するならCK-96MS。
・10g以上~100g以下のビッグベイトを使用するならCK-83XXHSといった感じです。
ちなみに、使用ラインは CK-96MSならPE1.2号、CK-83XXHSならPE2号を使用しています。
リーダーはどちらもフロロカーボンの25Lb.ですがナイロンでも可能。
時期的にバチ抜けパターンや軽めのルアーを使うイメージから冬季~春先は細いラインを使う方も多いのですが、使用するルアーとアプローチの仕方が、太いラインでのデメリットは少なく、逆に太いラインのメリットの方が多い釣り方です。
例えば、太いラインは、緩い流れでもしっかりと水を掴んで流れを利用したアプローチを行えたり、水の抵抗でラインが浮きやすくなることでデッドスローリトリーブでもルアーが沈み過ぎないためレンジコントロール性が高くなります。
使用時に釣果UPつながるテクニックなど
また太いラインを使うことで、ドラグを強く締めこめるのでランカーサイズがヒットした際にもファーストインパクトでスイープに強いアワセを入れられるため、確実にフッキングが決まりやすくなります。
大型になればなるほどバラシがほとんどない傾向にあります。杭が乱立する立ち位置やハードなストラクチャーのある場所でも強気なファイトが行えるので結果的にランカー捕獲率が上がっていると感じています。
ちなみに、ドラグはランカーサイズがヒットしても動かないほど締めこんでいて、ファイト中に状況に応じて緩めています。
強いドラグなら初期アワセ1発でしっかりとフッキングできるので、浅掛かりでフックが伸びることがほぼないので、今のところフックの伸びが原因でバラしたことはありません(多少は変形することもありますが)。
無事にキャッチ&リリースした後は緩めたドラグは、次のキャストに向けて再び締めこむのを忘れないようにしてください。普段から頻繁にスプールを触ってドラグの締め忘れが無いか確認する習慣を身につけてください。
加藤流こだわり
ハゼパターンではスローにボトム付近を通すためにX-80シリーズを使うのですが、使用する際にこだわっていることがあります。それは『リップが強く水を受けない』程度のスローリトリーブもしくはわずかな巻き抵抗を感じながらアプローチを行うことです。
リップに水を受けさせない理由は、リップ付きのルアーの多くはリップが水を受ける事で頭下がりの姿勢になり潜航するという性質があります。
私はその性質を発生しない速度(水抵抗)でリトリーブすることにこだわっています。
そうすることで潜行レンジを抑えることができ、またリップが水を受ける事で発生するウォブリングやローリングアクションを抑制する事で、X-80SWシリーズは、僅かな水流の変化等で柔らかいふらつきアクションを起こすので低水温で活性の下がっている大型のアフターシーバスに警戒心を与えずに捕食トリガーを誘発できるフィネスなアプローチが可能になるからです。
また、ゲンマ110SやX-80SWシリーズを主に使うアプローチ方法ですが、水深1.5m~2mのポイントなら潜行レンジ2.2mのKANATA SWもローテーションに加えてみてください。


KANATA SWの使い方はシンプルで2m程度のレンジまでタダ巻きですぐに潜るので、あとはゆっくりと巻くだけです。ボトムに当ってしまうのであればロッドポジションを上げてレンジコントロールしたり、リトリーブを数秒止めてルアーを浮上させ、再びゆっくりと巻き続けます。
シンキングミノーやシンキングペンシルとの違いは、巻きを止めたり、デッドスローではルアーが浮上するのでシンキングのルアーよりもよりスローにアプローチできるシチュエーションが増えます。
ルアーの特性を理解すれば様々な状況や地形変化に対応した狙い方ができるのでぜひ使ってみてください。
ちなみに今期はX-80マグナムとのローテーションで91cmをキャッチすることに成功。

KANATA SWは160mmと少し大きめですが、薄いボディなのでスローリトリーブで柔らかいアプローチを行うことで早春のハゼパターンにドはまりするミノーです。
また、今回紹介した加藤流ハゼパターンは、フィネスなアプローチ方法なので、バチが表層に出てこない底バチパターンやアナジャコパターン、レンジの深めなアミパターンなどとも近いアプローチになりますが、バイトは少ないなかがらも根掛かりのような鈍重なバイトが多いのが特徴です。
サイズも良い傾向にあるのでラインの傷等のチェックは頻繁に行ってください。
アミやバチ、小型のアナジャコは大型のハゼにとっても大切な食物となります。
早春の水中で繰り広げられている食物連鎖に密接にシンクロしているので、潮回りのタイミングや潮位に拘らずに狙えるハゼパターンも挑戦してみてくださいね。