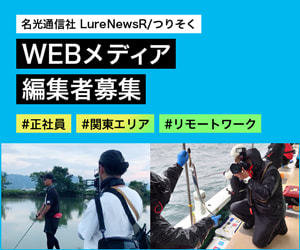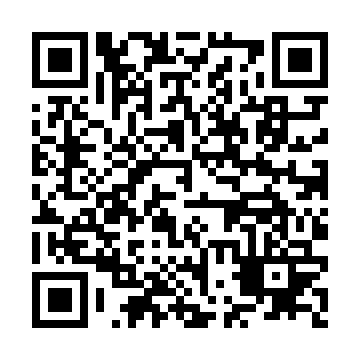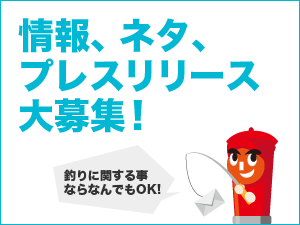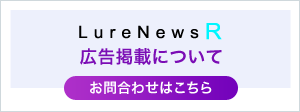投げて置いておくだけで「ふく」が来る。
にわかに話題となっている「ふく式」ですが、今回はその使い方を少~し掘り下げてお届け。
と言っても、投げて置いておくだけでしょ? ま、そう言われると元も子もないんですが…ほら、製作の意図などを知ることで、また違った景色が見えてきたりするかも、なんて。
そもそもは「ハゼ釣り用」として誕生

何もない所からポンッとこんな仕掛けのアイデアが出てくれば、それはそれでスゴイことなのですが。その実、しっかりとした背景というものがある。
もともと、江戸川放水路のハゼ釣り仕掛けとして開発が進められた「ふく式」。
上記の写真のような“牡蠣瀬”は見ての通り非常に根掛かりが多い。この牡蠣瀬をなんとか攻略できないかということで試行錯誤、あれこれ試す内にクランクベイトの根掛かりしにくさから着想を得て、リップに見立てたボディがシンカーをガードして根掛かりを回避する仕組みが誕生した…とのこと。

それはないだろ…みたいなプロトもあったりなかったり

…で。形状が決まってくると、今度はハリスが絡む。ここでもまた試行錯誤を重ねて、結果おしりの部分のワイヤーを逆反りに。こうすることで絡みが激減。
もう一つ。ワイヤーの先端に注目すると…ハリス止めとスイベルアイがある。これがちょっとしたギミックで、どうも開発を進める中で「浮く」=パンコイ(鯉を浮かせたパンで釣るゲーム)ができる!となり、それならば…ハリス止めにプラスして対大型魚用に直接ラインが結べる“欲張り仕様”になったと。


対象魚に合わせたモード(リグり方)
はい、ここで使い方です。上記でもサラッと説明した通り、対象魚やシチュエーションによって、それぞれ使い方があるんですね「ふく式」には。


まずは、ハゼやキスなど比較的小型の魚を狙う際のセッティングが「ハリス止めモード」。仕掛けをハリス止めにギュッと挟み込むだけなのでハリの交換もめちゃカンタン。


続いては、コイなど大型の魚を狙う際のセッティング「結束モード」。スイベルに直結することで、大型魚の強い引きにも耐えうることができる“強い”モード。


3つ目は食い渋りに効くという「半遊動モード」。こちらはラインアイには結ばずに通して、メインラインとその先の仕掛けを直接スイベルで結束することで、遊びができ魚に違和感なくエサに食いつかせることが可能。エサから竿先まで直接つながることで、アタリもわかりやすくシビアな状況に◎。※全遊動はワイヤーに負荷がかかりすぎて破損する恐れがあるとのこと
…後はエサを付けて投げるべし
使い方がわかれば、後は好きなポイントで好きなエサを付けて投げるべし。
その目の前のフィールドには何がいますか?ハゼ?キス?それともカワムツやコイ?仕掛けこそ「ふく式」ですが、釣り方やエサといえばそれぞれのターゲットの釣り方と基本的には変わらない。もっと言えばそれさえもわかりやすいメリットと言えるのではないかと。

キスやハゼ狙いであれば、ハリにゴカイやイソメをセットして投げる→そのまま置いておくもよし、食わせの間を意識しつつゆっくり巻いてきても良し。また、パンコイであれば、シンカーを取り外し結束モードにした上でパンをハリに付けて、エサが食われるのを待つのみ。あるいは、ふく式を飛ばしウキのように使えば…アジやメバルなんかもお手の物な訳です。
そう、可能性は無限大。ご紹介した使い方以外にも…あの魚にはあんな使い方、この魚にはこんな使い方、なんていろんな使い方が見つかればもっともっと盛り上がりそうな予感。
何が釣れるかわからない…そんな、釣り本来の楽しさを改めて教えてくれる「ふく式」。そういえば、使用する際のイメージが膨らみそうなこんな動画を終わりに変えて。
この投稿をInstagramで見る