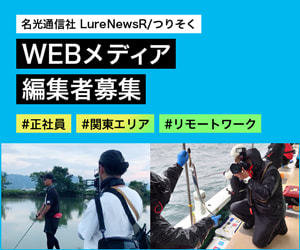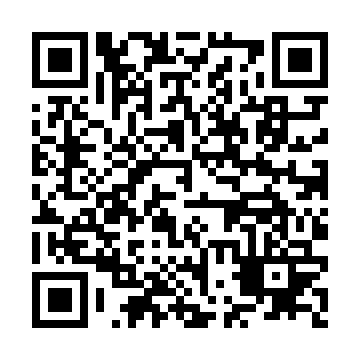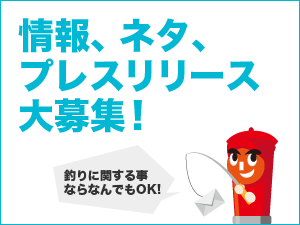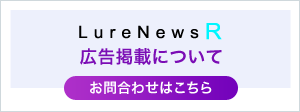琵琶湖湖北を舞台に10年以上、独自の経験と理論とテクニックを武器に数々のモンスターハントを成し遂げてきた。
「エスケープガイドサービス」のプロガイド、その人「山田 祐五」氏。
氏いわく、秘密にしておきたかった釣りがあるという。昨年1日4本のロクマルやナナマルを釣る事ができた、また5本で20㎏オーバーという驚愕の釣果が幾度となくあった。…すべて同じワーム、同じ釣り方で。


山田 祐五(Yamada Yugo ) プロフィール
2.5inchの衝撃
そのワーム・釣り方とは、もはや泣く子も黙る新たなジャンルとして確立した「カバースキャット」のボトムジャーク。
山田さんは2.5インチを使用。過去には何度も3.5インチで流した後で2.5インチを投入しデカバスを連続キャッチ。むしろ“2.5インチでしか獲れない魚がいる”とも。そしてその釣りは3月上旬くらいから、6月くらいまで有効だという。

どんな釣りが展開されているのか、その意図や使い方のキモなどを、本人に訊いてみました。
カバースキャット2.5インチのボトムジャーク/山田 祐五のケース
そもそも定番となっているカバースキャット3.5~4インチのボトムジャークが何を演出しているのかと言えば、イサザやヨシノボリなど総じて“ゴリ”と呼ばれる底棲生物だ。いつでも、どこにでもいる底棲生物を演出する“ゴリパターン”だから、そこにバスがいれば釣れる…そんなイメージではないだろうか。
2.5インチはさらにその釣りをブラッシュアップしたものと思えばいい。キモはシリーズ最小となるコンパクトなサイズ感。特にイサザがメインの5cmにも満たないようなマイクロベイトを捕食している時には、そのサイズ感がハマり極めて有効な釣りだ。

2023年は特にカバースキャット2.5inchのボトムジャークの好釣が目立つ。ほかのパターンに比べ優位であると感じている。

琵琶湖のゴリパターンが優位な年には特長的なパターンがある。それは「冬の積雪量が少なく、雪代による濁りが長引かない年」だ。今年のように3月上旬に濁りが取れるような年は、琵琶湖の沿岸部に生息している回遊性のベイト(特に稚鮎)が沖に出払ってしまう。したがって沿岸部に生息するベイトはニゴイ、真鮒、そして今回パターンのキモとなる「イサザ」が中心となる。
イサザは琵琶湖の多種多様な魚種の中でも「数」で言えば群を抜いて多い。普段は湖北の50~60mといった超ディープエリアに生息しているイサザが、産卵絡みで3月上旬に接岸する。沿岸部に大量に押し寄せてくるようなイメージを持ってもらいたい。沿岸部のハードボトムには、ほぼ全てイサザが張り付いていると思っていい。つまり、物理的にも捕食しやすいベイトが「イサザ」一択となる訳だ。

だから「2.5インチを選んで食っている」ように思う。釣れてくるサイズは40後半からMAX70前後まで。もちろん実際に3.5インチも投入はしており釣ってはいるが、統計的に好奇心旺盛なオスからのバイトの多さが目立つ。違うルアーなのかと思うほどに、でかいメスのキャッチ率は2.5インチが圧倒的に高い。