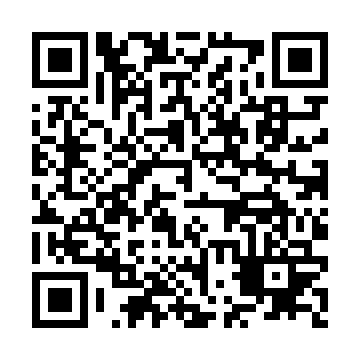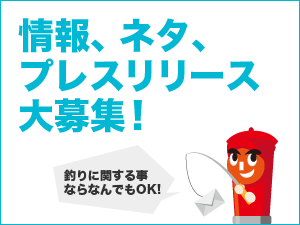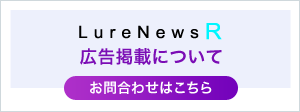計測マルチハサミについて、津本光弘さんに色々聞いてみた
先日「津本光弘」さんに直接お会いする機会があり、普段から記者自身もハピソンの津本式シリーズはモチロン、この「計測マルチハサミ」も多用しているので、記者が実際に普段使っていて疑問に感じたことについて、直接お話を伺うことに! 質問内容に沿う形で「津本光弘」さんから教えていただいたことをこれから紹介していきますね。
そもそも、「計測マルチハサミ」についてどう思われているのか? 伺ってみると、「津本光弘」さん自身も釣りに行った時に多用しているそうで、「現場で使うなら絶対コレ!」と言い切るほど。

特に5kg以下の魚を現場で処理をするにはカナリ向いているそうで、下処理のほとんどの工程ができ、なおかつ良く切れる。因みにですが「計測マルチハサミ」に使用されている刃は、刃物や金物が盛んな兵庫県・三木市に拠点を置く、ハサミのパイオニア「道灌(ドウカン)」製とのこと。切れ味からしても納得。さらにメンテナンスも簡単という、コレ以上の物があるのか? という理由で、日頃から津本光弘さんも「計測マルチハサミ」を使われているとのことでした。
続いてはこちらの質問。
釣り場で脳締めを上手くするコツについて教えていただきました。小型の魚ならまだしも、メジロやサゴシなどの中型魚種にもなると中々締まらず苦戦…、ということがこれまで多かったので直接コツを伝授していただくことに。教えていただいた結果、そもそも、上手くいかない時は、締め具を刺すポイントがズレていることがほとんど。それは大きい魚になるほど脳の大きさに対して頭が大きくなるので外しやすいそうです。

では実際、どこに締め具を刺すのか。
魚にはエラの横にエラと同じ方向を向いている線があります。そこを指で触りながら辿ると僅かな膨らみがあり、そこを越すと谷のように少し下がるポイントがあります。絞め具を刺すポイントはその下がる部分。

写真の魚はシマアジですが、大体指の部分へ締め具を刺すとシッカリ締まるそうです。因みに、魚が締まった時の判断基準として、動きなどでも分かったりしますが、弱っている時だと少し分かりにくいことも。そんな時、最も明確に判断できるのが目の向き。魚が生きている状態の時は目が若干下向きに。

写真のシマアジは締めた後の魚ですが、生きている場合の目の向き的にはこんな感じ。そして魚が締まれば目が真っすぐになります。

このように目が動けばOKとのこと! ぜひ締める時は参考にしてみてくださいね。
「計測マルチハサミ」を使うと現場での処理を快適に行うことができる訳ですが、実際のトコロ現場で魚の下処理を行う際、どういう順序で行うと魚の鮮度をより長く保つことができるのか? こちらに関しても伺うことができましたので、紹介していきたいと思います。
まず、魚が釣れた段階でスグに脳締めを行います。その後、エラ下を切って流血させ、水汲みバケツや大きめのクーラーなどがあれば、そこで15秒程魚を揺らします。コレを「フリフリ」と呼び、魚を揺らすことで体内の血を多く外へ出すことが可能。
刃を刺す部分(エラ下)

フリフリを終えれば氷水へ魚を仕舞えばOK。釣りをしている最中で時間をかけすぎない処理方法はこのような感じですが、もっと丁寧にするのであれば内蔵を取ったり、神経の血も抜いたりするのもイイかもしれませんが、新鮮な状態で魚を持って帰るのであれば、「脳締め→フリフリ→氷水へ入れる」だけで充分だとおっしゃられていました。

以上、「計測マルチハサミ」の紹介と津本光弘さんに直接伺った内容についてお伝えしました。これから暖かくなると共に釣れる魚の種類も多くなってきますので、ぜひ気になる方はお試しくださいね!
インタビューにご協力いただいた津本光弘さん、ありがとうござました!

ハピソン(Hapyson) プロフィール