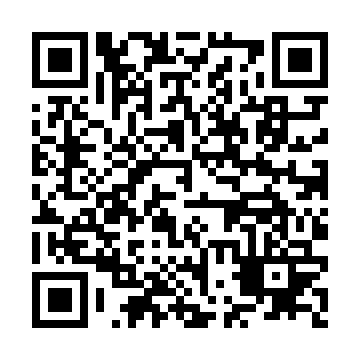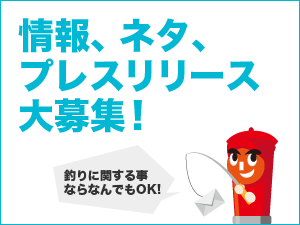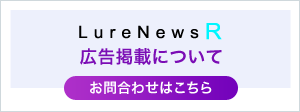こんにちは。松下雅幸です。
近年、僕のホーム琵琶湖では、北湖を含む全湖で様々な釣りが物凄いスピードで進化してきています。
中でもここ数年で定番化したのが“スピニングタックルでのPEラインセッティング”。
今まではフロロカーボンラインをメインにしてきた人達も、PEラインを使ったらそのメリットからフロロカーボンラインを使う頻度が減ってきている様に感じます。
中にはフロロでは無いと食わせきれない!という釣りも存在しているのは確かなのですが、PEラインを使う事により効率が上がり、デカバスのキャッチ率に貢献しているのは確か。
そこで、今回は僕なりの「スピニングタックルのPEラインを使った釣り」をご紹介させていただきます。

松下 雅幸(Masayuki Matsushita) プロフィール
琵琶湖スピニングタックルのPEラインセッティング
まず、PEラインを使うにあたりメリットはもちろんデメリットも存在するので、そのあたりはアングラー側が理解していないといけません。
1:10lbクラスのラインでも飛距離が出る。
2:糸の伸びが少ないのでディープやウィードエリアでもフッキングが決まりやすい。
3:リールのスプールのバックラッシュが少なく初心者でも扱いやすい。
4:比重が軽いので水面系の釣りにはストレスなく使える。
5:リーダーを太くすれば漁礁などの岩エリアでも良型のバスとのやりとりが楽になる。
6:感度が良い。
7、フッキングを少しミスしてもその後の対応がしやすい。
8、柔らかい竿でもファイトが楽。
1:リーダーを組まなくてはいけない。
(僕の場合FGノットをしているのですが素早く結べる様に練習が必要)
2:ロッドガイドに絡みやすい。
3:比重が軽い為、風で流されやすい。
4:比重が軽い為、ディープではルアーがフロロカーボンに比べ浮きやすい。
5:ラインが水に絡み、水を押すため魚に警戒されやすい。
これが僕が琵琶湖で釣りする上で感じているメリット、デメリットです。ただし、PEラインの種類やリーダーの組み方によってはデメリットを補える方法もあります。
デメリットを補えるPEライン
上記のPEラインのデメリット【3・4・5】に関して、今僕がメインで使っているサンラインの「シューター・デファイアー D-Braid」とリーダーの仕組みによっては、このデメリットをかなり補ってくれると思います。

サンライン公式「シューター・デファイアー D-Braid」詳細ページはこちら
サンライン公式「シューター」詳細ページはこちら
Dブレイドはナイロンラインと同じ比重なのでフロロほど…とはいきませんが、風に流されにくくディープでもルアーが浮きにくくなります。
また、僕は「シューター」の8〜12LBをリーダーとして組んでいるのですが、リーダーの長さを3mほど取る事によってフロロラインが沈んでくれディープでのボトムも取りやすくなります。更に、ルアーが付いている位置は3mほどのフロロリーダーなので警戒され難くなったように感じています。

フロロまでとは行きませんが、フロロラインとできるだけ同じフィーリングで使いたい方はこのセッティングをお勧めします。
PEラインが必要不可欠なソフトジャークベイトのミドスト
近年特にスピニングのPEラインでフューチャーされている釣りの一つが、デプス「サカマタシャッド」のミドストの釣り。

ピンテール系のワームを使用した1.8gクラスのジグヘッドでのミドストは今までもありましたが、「サカマタシャッド」の場合は5g前後といった重めのジグヘッドでディープレンジをスピーディーに探っていくため、今までのタックルバランスでは難しいのです。
これは、比較的ディスタンスをとる釣りで、更にディープの釣りになるのでフロロカーボンラインだと糸が伸びてしまうからです。また動きにキレを出し難く、だからと言ってサオを硬くするとリズムも取り難くなり、1日やった時の疲労度は計り知れず…。
タックルバランスとして、フロロに硬いサオというのは僕の中ではあり得ません。
そこで、比較的柔らかくリズム良く振れるサオにPEラインを組み合わせます。これにより、動きのキレが出しやすく、1日やっても疲れにくい。さらに、ディープでもデカいバスの口に針を貫通させやすいタックルバランスとなるわけです。

もう、今の琵琶湖はスピニングPEタックル無しでは考えられなくなりました。フロロと同じまでとはいきませんが、少しでもフロロとフィーリングを合わせたい方は「シューター・デファイアー D-Braidに3mほどのリーダー」この組み合わせを、ぜひお試しください。


サンライン(SUNLINE)